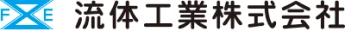技術資料 積流量計 構造と作動原理
面積流量計の構造と作動原理
上向きの傾斜をもつ測定管(通常テーパ管と称する)内に自由に昇降できるフロートを収め、それを適当な支持具で組立てたものが面積流量計です。
これに下方より上方へ流体(液体、気体、蒸気)を流すとフロートはその前後に生ずる圧力差による力のために上ヘ押し上げられますが、フロートが上方へ移動するにつれてフロートとテーパ管との流通面積が増加するのでそこを通過する流体の速度が減り圧力差が減少してフロートはその可動部の質量と圧力差による力との均衡した位置で静止します。
この時のテーパ管内のフロートの位置によって決まる流通面積と通過する流量とは一定関係にあるので、その位置を検出して流量を測定することができます。
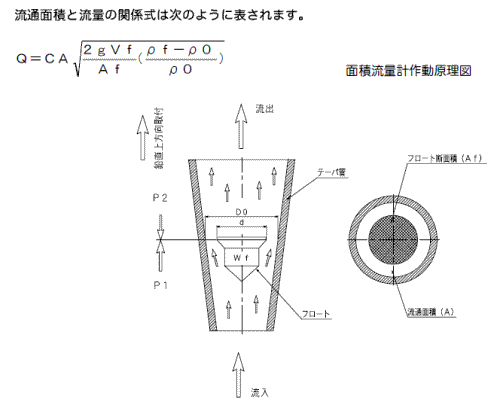
即ち、流出係数Cがー定のとき流量の変化と流通面積との関係はQ∝A と一次式で現されます。
Q:流体の体積流量
C:流出係数
A:流通面積
g:重力の加速度
Af:フロートの最大径部断面積
Vf:フロートの体積
ρf:フロートの等価密度(=Wf/Vf)
ρ0:測定状態にあける流体の密度
Wf:フロートの質量
従ってテーパ管の昇程と流量との関係はテーパ管の傾斜度、流出係数を考慮し、ほぼ均等に近い曲線として得られます。
本型式の流量計は上記のように流通面積が変化することから面積流量計とも呼ばれ、JIS規格の呼称はフロート形面積流量計となっております。
日本工業規格 JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計
上の内容を式で展開すると、フロートが、ある位置でつり合っているときフロートにかかる上向きと下向きの力が等しいから
Wf+Af・P2=Af・P1 から差圧 h は
h=(P1-P2)=Wf/Af ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
ここで
P1:フロート上流側圧力
P2:フロート下流側圧力
Af :フロートの最大径部断面積(πd2/4)
Wf:フロ-トの有効重量
h :差圧 (水頭圧 m ) [水頭圧 1m = 9.8067 kPa ]
一方、管内に流れる流体の体積流量Qは
・・・・・・・・・・・・・(2)
ここで
C:流出係数
A:流通面積で(π/4)・(D02-d2)
v :フロートとテーパ管の隙間の流速
ρ0:測定状態における流体の密度
g :重力の加速度
D0:フロート平衡位置のテーパ管の最小径
d :フロートの最大径部の直径
また
フロートの等価密度を ρf
フロートの体積を Vf とすると
Wf=Vf(ρf-ρ0) ・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
式2に式1及び3を代入すると流通面積と体積流量の関係は
・・・・・・・・(4)
質量流量で表すと W=Q・ρ0 より
・・・・・・・(5)
が求められます。
面積流量計をご注文いただき製造するには流体の「密度」、「粘度」は慨知でなければなりません。流体の「密度」、「粘度」が不明な流体では流量計を製造することはできません。
面積流量計を製造するうえで流体の「密度」が慨知の必要性があることは上の式内に ρ0 が存在することでご理解いただけると思います。
また、これはベルヌーイの定理によっており、流量は差圧と流体密度の平方根に比例していますので、流体密度 ρ0 が製作時の設計仕様と異なる値で使用した場合は流量に誤差が生じることも判ります。
備考
1.上の式の h 差圧の単位は水頭圧 m を用いています。Pa(パスカル)を用いた場合には式の中の g 重力の加速度 m/sec^2 が省かれます。
上の式の説明は日本工業規格 JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計 を参考にしていますので、g が含まれています。
面積流量計ではフロートの上下の圧力差(差圧)hは常に一定です。
流量計の圧力損失はフロートの上下の圧力差(差圧)に流量計内部の流出抵抗をプラスしたものですが、一般形式の流量計では構造が簡単なことから流出抵抗は、ごくわずかですので、最大流量時でフロート上下の差圧(h)の15%程度プラスした値となります。
一般形式では面積流量計の製作する上で設計上で算出した差圧hに15%程度をプラスした値が流量計最大流量時の圧力損失と、お考えください。
最小流量時(10%)~最大流量時(100%)の間は、ほぼ比例関係となります。
構造が複雑な形式や、流量計サイズに対して流量レンジが大きい形式になると差圧(h)の70~80%プラスした値となりますが(特殊形式)面積流量計の正確な圧力損失を知るには実際に計測する必要があります。